現状維持から抜け出す方法
- なるせゆうや

- 2024年8月15日
- 読了時間: 4分
【現状維持から抜け出す方法】
今、生徒さんのブログを読んでいて、
そのブログに僕が2020年に開催した
高尾合宿に行った感想が
書いてありました。

『そーいえば、
彼女にブログを紹介された時、
高尾合宿の時から書いてたって
言ってたようなぁ〜(笑)』
僕が2020年に高尾合宿を開いたのは
完全に『遊び』でした(笑)
そして『気分』で
やりました(笑)
彼女自身『人生を楽しむ!』
をキーワードにしているし、
僕自身も高尾合宿を『遊び』のつもりで
開催して、
改めて『遊び』ということについて
そのブログを読んで
考えさせられました。
それが今回のテーマである
現状維持から抜け出す方法に
直結しています。
現状維持は自分にとって
心地よいゾーンに居続けることで、
自分にとって心地よいゾーンなので
慣れ親しだゾーンではあるのですが、
慣れているがゆえに
変化に乏しくなります。
そーすると同じ毎日や
同じルーティンの繰り返しになり、
まぁ、俗に言う『マンネリ化』が
進むわけですね。
ただ『遊び』というのは
完全に現状の外側に
楽しさやワクワクを求めて
進んでいくことになります。
子供を見ると分かりますが、
子供たちは『遊ぶ』ことで、
『新しい楽しさ』を追及し、
そして、『新しい世界』に
どんどん進んでいきます。
大人に比べて
子供たちの方が
スマホやネットに強いのは
ハッキリ言って
中学生や高校生の時の遊びの結果です。
スマホで遊んでいたから、
彼らはスマホやネットやアプリに
強くなっていき、
60歳のどこぞの会社の社長よりも
20代の新卒の若者の方が、
スマホにも、ネットにも、強いのです。
知り合いに
『祭り好き』の人がいるのですが
日本中の祭りに
顔を出しているそうです(笑)
それは、本当に、
彼女にとってただの『遊び』ですが、
でも、その『遊び』のおかげで
日本中を飛び回り、
おそらく『祭り』
という文化にも正通して
思いっきり、彼女の世界を
広げまくっています。
それは、毎日を同じルーティンで
現状維持をしていたら、
まったく見えなかった世界でしょう。
つまり『遊び』が
僕らの現状維持をぶっ壊し、
新しい世界の扉を
開いてくれるのです。
良く言われる話ですが、
魚が陸に上がった時の進化は
現状維持の理論では
まったく説明できないと言われています。
ダーウィンが話している理論だと、
『環境に対する最適化』なので、
『今の環境に合った自分になる』
ということなのです。
でも、それでは
魚は水中という環境に
最適化してしまい、
わざわざ、陸に上がることは
あり得ないのです。
つまり、現状維持の最適化の理論では
動物は進化しない。
動物もだし、僕ら人間も
進化しようと思ったら、
『最適化の超越』
『現状維持の超越』
をしていく必要があります。
つまり『遊び』によって
現状維持の外側に行くのです。
僕は昔、良く仕事帰りに、
『今日はいつもと違う道で帰ろう!』
ということを繰り返してました。
家に帰るのは少し遅くなるけど、
新しい道を通ることに
新鮮さを感じていたんですね。
そうやって、新鮮さを求めて、
いつもと違う道を通っていたら、
可愛いネコちゃんたちを
いっぱい見つけました(笑)
元々、僕は犬好きだったのですが、
その違う道を通ったおかげで
ネコ好きになりました(笑)
そして、しばらくしたら
ネコを飼っていました(笑)
ほら、この話は全部、
『遊び』の結果、
現状維持から抜け出して行くプロセスです。
『違う道を通る』という遊び
↓
『可愛いネコに出逢う』という現状の外
↓
『ネコ好きになる』という現状の変化
↓
『ネコを飼う』という現状の変化
コレは僕の些細な例ですが、
『遊び』によって『現状維持』が崩れ、
『現状変化』が起きる
そのプロセスがこの話に詰まっています。
そもそも、高尾合宿に来てくれた
その生徒さんも、
高尾合宿に参加するという
遊びがなければ
僕と出逢うこともなかっただろうし、
そもそも僕が気まぐれで
高尾合宿という遊びをやったことが
僕の現状も彼女の現状も、
変化させてしまったのです。
これらの話からも分かるように
『遊び』には
『現状維持を抜け出す力』が
あります。
よく自己啓発を学ぶ人は
『現状を変えるために必死に努力!』
って考えているけど
・努力なんかしたら、
・意識が凝り固まって、
・視野が狭くなるので、
・ますます現状維持されてしまいます。
真逆です(笑)
・努力をやめて、
・意識を緩めて、
・視野が広くなり
・遊ぶことで現状を飛び出る
ことが大切なんです。
ということで、
いっぱい遊んで、楽しんで、
魚が陸に上がったように
素晴らしい進化をして行きましょう(笑)!
今日もありがとう😊✨
なるせ
『高尾合宿という“遊び”で感じたこと』


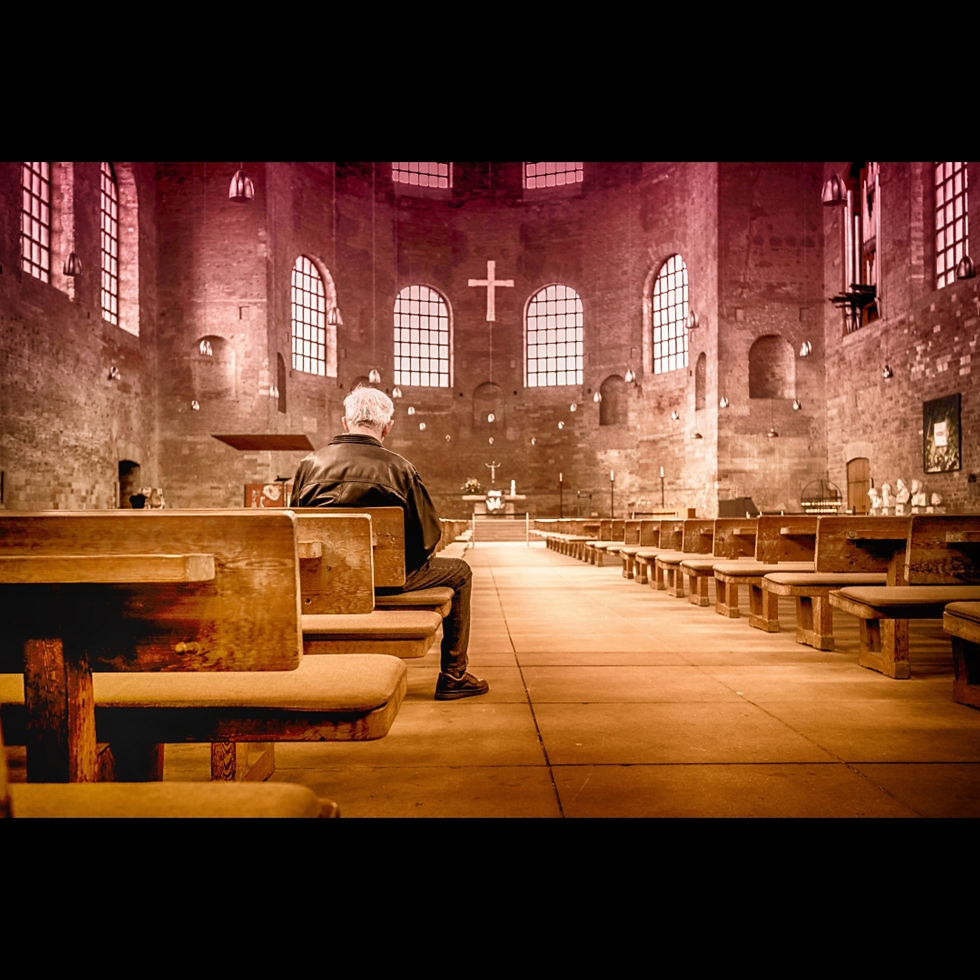

コメント